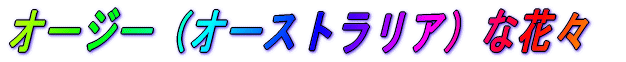
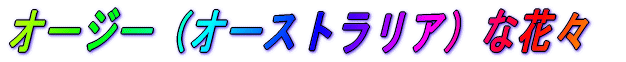
今年3月末にオーストラリア東部のゴールドコースト、ブリスベーンからシドニーへ行ってきました。
初めての南半球。季節も日本の正反対で、まだ夏の余韻の残る初秋の気候でした。
海岸から丘陵地、市街地の花を楽しんできました。
また、南半球ならではの楽しい経験もしました。
とにかく、底抜けに明るく、そしてマイペースなのがオーストラリア。
では、ワイルド(wild)でマイルド(mild)なオージーフラワーをお楽しみください。
マウンテン・デビル (Mountain Devil) (シドニー/ クーリンガイ野生植物園) |
このオドロオドロシげな名前の花。種の形が悪魔の顔に似ていることからついたようですが、日本ならさしずめ「赤鬼草」とでも呼ぶのでしょうか。 実  蕾(クリックで拡大します) 実も蕾も鬼の角のようです。 |
クーリンガイ野生植物園(Ku-Ring-Gai Wildflowr Garden)はシドニーの中心部から地下鉄で20分ほど行った清閑な郊外の住宅地の中にあります。渓谷をうまく利用した広さ123ヘクタールの園内は、「自然から何も足さない、何も引かない」状態で保存されており、山火事さえも自然の一部として放置されれています。そのため、花の種類は多くありませんが、2時間のトレイル散策で出会った花はオーストラリアの宝石のようでした。 |
|
| スモール・クロウェア (Small Crowea) 日本では園芸店で「サザン・クロス(南十字星)の名で売られていますが、これは似たような花で4弁のブロニカと間違えららたもの。これは5弁花です。また、オーストラリアではサザン・クロス(Southern Cross)は別の花です。 本当のサザン・クロス |
 |
||||
ブラシの木 (Bottlebrush) 最近は日本でもオーストラリアの花が見られるようになりましたが、最初に渡ってきたのがこのブラシの木。公園だけでなく住宅地の中にも植えられています。ビンの洗浄に使うブラシそっくり。ということは・・・ビン洗いのブラシは「ブラシの木」の発見前からあった?!ことになります。  |
|||||
 |
ティートリー (Tea tree) 直訳すれば「お茶の木」。日本のお茶とはまったく違います。どちらかといえば、小梅や庭梅に近い形状の花です。でも、これが上のブラシの木の仲間(ミャータセア Myrtaceae)だと信じられますか? |
||||
フクシア・ヒース (Fuchsia Heath) 日本で売られている園芸種のフクシアはぽってりした下膨れ美人。さすが野生の花はスレンダーです。  (日本の園芸種) |
 |
||||
ミモザ(Sunshine Wattle)  日本で早春に黄色い花房をつけるミモザ(銀葉アカシア)はオーストラリアが原産。この仲間のゴールデンワトルはオーストラリアのほぼ全土で見られ、オーストラリアの国花となっています。
|
|||||
 |
松葉ジーバング(Pine-leaf Geebung)
これもユニフォームと同じ配色。松の花のようですが、マウンテン・デビルの仲間(プロテアセア proteaceae)です。プロテアセア属だけでなく、他の同種の属であっても花の形状が大変違った植物が多くあります。これはオーストラリア大陸が早い時期に古代アフリカ大陸から分かれたため独自の発達進化が進んだためです。 オーストラリアの動物も皆、有袋類という一種類だけですが、その形状は(今は絶滅した)フクロオオカミからカンガルーまで大変バラエティに富んでいます。 |
||||
新大陸オーストラリア。始めてオーストラリアを探索したのが英国人船長クック。先住民族であるアボリジニを「国を構成できない野蛮人」として、土地を簒奪する嚆矢を演じることになりましたが、部下に植物学者を帯同して生物学的調査を実施しました。(後のダーウィンもこうした探検隊付き学者でした) そこで見たものは・・・現代人もびっくり。これは蜘蛛(クモ)か、宇宙船か! 名称不明(タスマニアン・ワラタにも似ていますが・・・)  (ここまでの画像はすべてクーリングガイ野生植物園で) |
|||||
| クック船長と一緒に来た植物学者はジョゼフ・バンクス。オーストラリア東部を探検し、多くの(ヨーロッパ人にとっての)新種の植物を発見。その中に彼の名をつけたバンクシア(Banksia)があります。彼の名を取った町(バンクス・タウン−水泳のイアン・ソープが居住)がシドニーの南西部にあります。近くの湾はボタニー(植物学)湾。 |
|||||
| バンクシア(Banksia) 形は「ブラシに似ていますが、ブラシの木とは別の種類。  (ゴールドコースト メインビーチ) |
 |
||||
 |
グレビレア(Grevillea) 最近日本でも見かけるようになりました(オフィスの近くの小庭園にありました)。バンクシアと同じ仲間(proteacea)ですが、色も形も大きく違います。また、グレビレアの中でもいろいろな亜種があります。 ← これはボッグ・グレビレア(Bog Grevillea) (ブリスベーン マウント・クース植物園) |
||||
さまざまなグレビレアたち(クリックで拡大します) |
|||||
「オーストラリア」と聞いてすぐ思い起こすのが「コアラ」。そのコアラが食べるのがユーカリの葉。日本の松と同じようにいたるところで見られます。堅い木なので電信柱(コンクリートではありません)や枕木などに使われています。 また、葉からはユーカリ油という鎮痛効果がある油が取れます。だからコアラ(時としてオーストラリア人)はその効果でスローモーで怠け者だ、と陰口をたたく人がいます。 ユーカリの種は堅く、熱を与えないと発芽しません。乾燥地帯のオーストラリアは山火事−ユーカリの樹皮は油分が多く、風などで擦れると発火します−が多いため、適者生存でそうなったものと思います。 「身(実)を焼いて子孫を残す」フェニックス(不死鳥)のような植物です。 |
|
| ユーカリ(Eucalyptus) 大木 (シドニーで一番古い木?) 花と葉   (オペラハウス近くの王立植物園) (ブリスベーン マウント・クース植物園)) |
|
| ユーカリはブラシの木と同じ仲間(フトモモ科)ですが、その種類は500種類以上もあり、中にはきれいな花をつける種類もあります。 グム・フラワー(Gum Flower) (ゴールドコースト パラダイスウォーターズの公園) |
|
 (これは野生ではありません) (これは野生ではありません) |
|
| カンガルー・ポー(Kangaroo Paw) コアラと並んでオーストラリアを代表する動物がカンガルー。 昔、カンガルーと人間のボクシングの試合がありましたが、そのときのカンガルーのグローブをはめた前足(ポー)とそっくりです。 カンガルー・ポーは本来はオーストラリア南西部(パースのあるところ)に自生しています。 (ブリスベーン マウント・クース植物園)) |
 |
| |
|
| オーストラリアは移民の国。最初の移住民は12万年前に南インドから渡ってきたアボリジニ。その次が、250年前のイギリス人。その後はヨーロッパ各国や大英連邦諸国から続々と。近年では「白豪主義」を廃止したこともあって、ベトナムや香港出身の中国人などアジア系の移民が増加しています。 花も同様に、こうした移民たちと一緒にオーストラリアにやってきました。したがって、これら移住花は、最初の上陸地である海岸や都市部で多く見られます。 グロリオサ(Gloriosa) 別名: ユリグルマ アフリカが原産のユリ科の花(ジンバブエの国花です)。喜望峰を回ってやってきた英国人が持ち込んだものかもしれません。花弁が炎のように巻き上がっている形状からFlame Lily(炎のユリ)とも呼ばれています。根には毒を持つので食べられません。 ゴールドコーストの海岸では群落を作っていました。日本のお花屋さんが見ると羨ましがるでしょうね。  (ゴールドコースト メインビーチ) (ゴールドコースト メインビーチ) |
|
ポインセチア(poinsettia) (野田様からのご報告) グロリオサの隣に咲いていました。北半球ならクリスマスの頃に色づきますが、水着のサンタが出るオーストラリアでは季節は無関係。 赤いのは葉で、花は中央で粒状になっています。メキシコが原産。アメリカ合衆国の初代メキシコ公使J・R・ポインセットの名から名づけられました。 白花もありました。  |
 (ゴールドコースト メインビーチ) |
 |
フサナリツルナスビ (Brazilian nightshade) 別名: 瑠璃色蔓茄子 (野田様からのご報告) 藤の花のようでもあり、アサヒカズラ(朝日蔓)のようでもありますが、ヤマホロシに似ているのでナス科。南米ブラジルが原産です。 (ゴールドコースト メインビーチ) |
名称不明 海岸の砂地に咲く花。日本な赤いハマナス(バラ科)でしょうが、葉の形状から見てバラ科の植物ではありません。オーストラリアのワイルドフラワー図鑑にも載っていません(上の2つも同様)。 (ゴールドコースト メインビーチ) |
 |
日本でもオーストラリアの花木が植えられているように、市街地に咲いている花々はほとんどが海外からやってきた花です。しかし、現地化により母国の花とは姿かたちがかなり異なっています。 野牡丹 (ノボタン) ブラジルが原産のノボタンは今や日本のどこにでも見られるポピュラーな花ですが、高さはせいぜい2m程度。ところがここでは優に30mを超える大木となります。(左下の自動車と比較してみてください) 住宅の前庭に植えられているのを見ると、一瞬「ジャカランタ」かと思ってしまいます。(ジャカランタは春咲きます) 競争相手がなかったからすくすくと育ったのでしょうか、それとも・・・オージーガールの胸(中年になれば腰)のようにこの土地は何でも大きくしてしまうのでしょうか。 |
|
  (シドニー ドメイン) |
|
日本から渡ってきた花もあります。 |
|
| 山茶花 (Sasanqua) 住宅の生垣に好んで植えられています。日本では晩秋から初冬にかけて咲きますが、オーストラリアでは(気候的に)夏の終わりです。気が早いですね。 明治の初め頃、椿と一緒に日本からオーストラリアに渡ってきました。 (シドニー ビレッジグリーン) |
 |
あら、椿も・・・ |
と、思うと躑躅(ツツジ)まで |
さてまた・・・菫(スミレ)も咲いています。 |
夏の花、冬の花、そして春の花が一緒に咲き乱れています。いくら南半球だからといって・・・赤道を越えた途端に母国での季節に合わせて咲くDNAを脱ぎ捨ててしまったのでしょうか。 花々にはパラダイス(天国)なのでしょうか、それともインフェルノ(地獄)か・・・・ (ブリスベーン マウント・クース植物園) |
スライドショーがあります。 ここをクリックしてください。(パスワード必要) ちょっとマイナーなオーストラリアの動物たち |
|
| コアラやカンガルーがオーストラリアを代表する動物だとしたら、一世を風靡した「エリマキトカゲ」はマイナーの代表格。乾燥気候のせいか爬虫類がたくさんいました。 | |
| 結構愛嬌のあるイグアナ | 体長2m。出くわすとちょっと怖いドラゴン |
 |
 |
| (ブリスベーン マウント・クース植物園) | (ブリスベーン マウント・クース植物園) |
NHK『ダーウィンが来た』で紹介 オオコオモリ |
ゴミ漁りでカラス並に嫌われている クロトキ |
 |
 |
| (シドニー 王立植物園) | (ゴールドコースト パラダイスウォーターズ) |
北半球から赤道を越えて南半球に入ると面白い経験ができます。そのひとつが「日陰」。北半球では北側にできる日陰も南半球では南側です。従って「家は北向きを良しとし」ます・・・これは理解できましたが、月の満ち欠けも右側(上弦)からでなく、左側(下弦)から満ちてくるのにはちょっと驚きました。 |
||
| 3月21日 | 3月23日 | 3月26日 |
 |
 |
 |
| (なお、トイレや風呂の排水の渦は北半球では反時計回りで、南が時計回りという説がありますが、今回ホテルの洗面台で実験してみましたが確認できませんでした) | ||
頂き物コーナー
ヒマラヤの花です。大岡さんからいただきました。私も世界遺産の「花の谷」へ是非行って見たいです。
アスターヒマライクス(標高3500〜5000m) |
|
エーデルワイス(薄雪草)  |
リンドウの仲間  |
菊の仲間 日本の高山植物の「兎菊」に似ています。 これは「山母子」に似ています。  |
 |
蘭の一種でしょうか・・・ これは???  |
|
もっとヒマラヤの花を見たい方はここをクリックしてください。 |
|
いよいよ梅雨明け間近。夏山シーズンの始まりです。次回は「雲上の宝石」をお届けします。