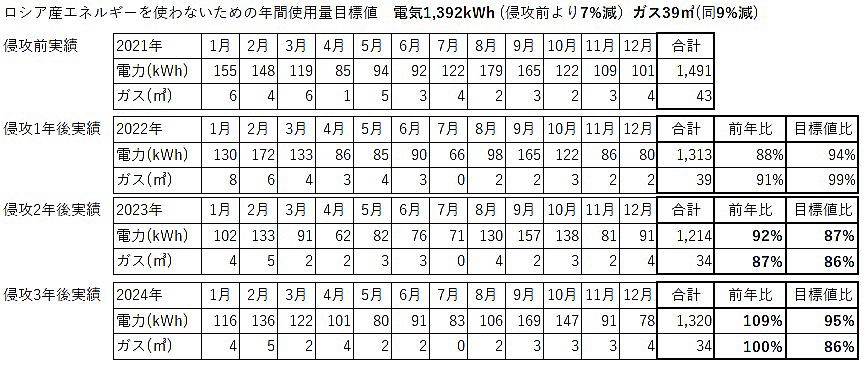今から約7~6万年前に気候の乾燥化で食料や水が得られにくくなったことで、人類、ホモサピエンスはアフリカを出た。当時は陸地であったベーリング海峡を約2万年から18,000年前に渡り、パナマ地峡を超え、そして長い旅路の末、約13,000年前南アメリカ大陸の最南端パタゴニアに到達した。地球の外周の3/4になる3万km超を5万年近くかけて踏破したグレートジャーニーであった。彼らがそこで見たものは・・・花咲き乱れるパラダイスだったか、それとも寒風吹きすさぶ荒野であったか?
昨年(2024年)12月、世界の果て(Fin del Mundo)の花を求めて、チリを最北のアルティプラーノから最南端マゼラン海峡まで4,000㎞超を3週間かけて縦断しました。今回はその前半、チリ北部と中部の花々をご案内します。 |
|
|
チリの地理
日本から見て、チリは地球の反対側に位置している(真裏に当たる対蹠点はブラジル南部とアルゼンチン東岸の大西洋上)。時差も丁度12時間異なる。
国土面積は約75.6万㎢で日本の約2倍。東西が平均200km(90km~445km)、南北4300kmと左図のように細長い。北はペルー、東はボリビア、アルゼンチンと国境を接し、国境に沿って5,000mクラス(最高地点はアコンカグアの6,959m)のアンデス山脈が連なっている。西は太平洋に臨み、直ぐ沖合に深さ8,000mを超える海溝が海岸線に沿って走っている。この海溝は南米プレートと太平洋プレートの境界となり、太平洋プレートの沈み込みにより大陸側の地殻が盛り上がり、アンデス山脈を形成している。現在もアンデス山脈は年に数ミリから数センチ隆起を続けている。このため、チリでは地震や噴火が頻発するとともに、砂漠から氷河地帯まで変化のある気象状況を作り出している。
(北部)
南緯18-30°に位置し、東からの貿易風がアンデス山脈にぶつかって湿気を落とし、乾いた風を吹き降ろす。風下に当たるアンデス山脈西側は乾燥地帯となり、世界で最も乾燥してるといわれるアタカマ砂漠がある。植生は貧弱で乾燥に強い種しか見られない。その一方、銅や岩塩、硝石など鉱物資源が豊富である。
(中部)
南緯30-37°に位置し、亜熱帯高圧帯に入る。このため、冬は雨が降るがその他の季節は乾燥し、地中海気候となる。アンデス山脈の融雪を利用した灌漑が発達し、小麦やかんきつ類の栽培が盛ん。同じ気候や農業様式を持つスペイン系の住民が多い。
(南部)
南緯37-50°。偏西風が運ぶ海からの湿った風のお陰で、この地域の北側(南緯37-45°)では温帯雨林が広がる。気候は湿潤冷涼でイギリスや北欧に似ている。産業も林業や牧畜業、漁業が中心で、イギリスの田園を思わせる風景が広がる。日本の援助で始まった鮭の養殖(自然状態では南半球に鮭はいない)は主要な輸出品目となっている。一方、南側(南緯45-50°)では湿った空気は雪となり、平均標高2000mの海岸山地に積もった雪は万年雪となり、氷河を形成する。この地域はパイネ山群の観光施設を除けばほぼ無人地帯である。
チリ南部で雨や雪を降らせた偏西風はアンデス山脈を超えるとカラカラに乾いた風となりアルゼンチンに吹き降ろす。このため、アルゼンチン南部では樹木のない荒涼とした大地―パタゴニアが果てしなく広がる。
(最南部)
南緯50-55°。チリの最南端に位置し、南極から吹く強烈な極東風(船乗りから「吠える40度」と恐れられてきた)により、背の高い樹木は育たず、荒涼とした草地が拡がる。だが、この草は牛や羊の食料として適しているため牧畜業が中心的な産業となる。この他、フィヨルド湾での漁業や観光業もある。(チリ政府は、国際条約で領有を主張できない南極大陸の一部を自国としている)
|
チリには「3Good W」があるという。その一つは気候(Weather)で、晴天が多く気温も穏やかということだ。私が滞在していた3週間の間で雨に降られたのはわずか1時間であった。ただし、これは冬に最南端部に行ったことのない人の意見である。もう一つはワイン(Wine)、寒暖差が大きく土地がやせていることで美味しいワインができる。旅行中毎日1本、空けていた。ただ、値段は日本とあまり違わないのが腑に落ちない。そして最後が女性(Woman)。街を歩くと様々な人種の人々に会う。髪の黒いスペイン系の人、肌が白い北欧系の人、インカの末裔らしき人、そして混血の人々。みな、なかなかの美人である。血が混じることで美人が生まれやすくなるのだろうか。またラテン系の陽気な性格。確かに魅惑的だが、残念ながら私的な関係を作る時間がなかったので最後のWについては評価できない。ただ、南米全般に言えることだが、女性の社会的地位はまだまだ低いようだ。
今回巡ったあと、私はこれとは別の「3Good W」があることに気づいた。それは・・・
Water(水)―北部は砂漠であるが、国境に沿った火山群は万年雪を頂く。その融雪は灌漑施設を通じて麓の農園や果樹園を潤している。また、数年に一度だがエルニーニョ現象が発生した時、海から霧が押し寄せ、砂漠を一面の花畑に変える。南部に降る雨は森林を育むほか、寒流のフンボルト海流は深海のミネラルを供給し、海に栄養分を与え、水産資源を保全している。さらに、現在も拡大する氷河は温暖化防止や二酸化炭素吸収に寄与している。
Wind(風)―上述したようにチリには3種類の恒常風、北部の貿易風、南部の偏西風そして最南部の極東風が吹く。吹く方向の違う風はアンデス山脈と協働してチリに多様な気候をもたらし、様々な植生を分布させる。だが、チリだけあって、風で舞い上がる塵(ちり)や埃でカメラのレンズ交換ができず、2台を持ち歩かなければならず、重くて閉口した。しかし、この塵が貿易風に運ばれて、中の鉄分が海上に落ちると植物プランクトンの栄養となるため、チリ沖は世界有数の漁場となっている。この魚を求めてやってきた水鳥たち(Wing)が落とした糞(ふん)が火薬や肥料の材料となる硝石としてチリに莫大な富をもたらしたことも忘れてならない。
Woods(森林)―南部に広がる温帯雨林地帯には広葉樹のほか、チリマツ(アロウカリア・アラウカナ)やヒノキ科のアレルセなどの針葉樹が密生する。こうした針葉樹は建材や家具材に利用されるほか、並木や公園樹として植えられている。また二酸化炭素吸収にも寄与している。特にアレルセは高さ50m、幹回り11m、寿命3200年以上と縄文杉にも匹敵する巨木にもなる。森林火災が頻発する中部・地中海気候地域では植林や森林再生プロジェクトが進められている。
|
初めて訪ねたチリであったが、その多様性と豊かさはまさにワンダーランド(Wonderland)であった。
|
 |
チリ北部はかつてはペルーとボリビアの領土であったが、1879年-1884年に起きたペルー・ボリビア連合軍との戦争(太平洋戦争という)で勝利したチリが割譲させた。海のないボリビアに海軍があるのはこの名残である。 |
|
チリの首都、サンチャゴからアリカに飛び、レンタカーで国道11号線を東に向かう。この道路はボリビアと太平洋側の港湾を結ぶ唯一の国際道路で、ボリビアの生命線。鉱物資源を積んだ大型ダンプや石油タンクローリーがひっきりなしに通る。
(クリックで拡大)  |
 |
|
海抜0mのアリカから標高3500mのプトレへ一気に上る。標高3000mまでは谷底の緑をのぞくと草木1本もない砂丘地帯が続く。 |
 |
|
道路わきには十字架を立てた小さな祠が点々と続く。交通事故の現場だ。日本で地蔵像が祀られているようなもの。峠道の急カーブを曲がり切れず大破したコンテナ車もあった。
交通量の多さと過酷な労働環境が原因であろう。宗教心の濃さもあるかもしれない。 |
 |
| 最初に出会った植物は・・奇妙な形をした木? |
|
|
|
|
ブラウニンゲア・キャンデラリス
Browningia candelaris サボテン科
サボテンの1種で、ペルー南部とチリ北部でしか見られない。腕(葉)をくねらせた姿は乾きに苦しむヒドラの頭のようにも見える。
幹の周囲は鋭い棘で囲われていて、ビクーニャから身を守っている。
|

(新芽) |
|
| こんなカラカラに乾いた大地にも根を下ろし、花をつける植物はある。 プトレへの途上で見た花々。 |
 |

ソラヌム・リコペルシコイデス
Solanum lycopersicoides
ナス科、トマトの野生種。
|
 |
 |
タラサ・オペルクラータ 
Tarasa operculata アオイ科
アオイ科の花。8ヶ月間水なしで生き続けることができる。
(標高2800m) |
 |
キスタンテ・アラマラントイデス
Cistanthe amaranthoides スベリヒユ科
スベリヒユの仲間で、乾燥にめっぽう強い。エルニーニョが発生し、アタカマ砂漠に雨が降ると、数週間後砂漠はこの近縁種のCistanthe grandifloraで埋め尽くされる。数年に一度発生するエルニーニョ現象に合わせて訪ねたいものである。
(標高2800m) |
|
乾燥した大地も標高3000mを超すあたりから様相が変わってくる。イネ科やスゲ科の植物がまばらに現れ始め、標高が上がるに従って密度を増し、棘の多い灌木も現れ始める。頂上付近に発生する雲からの湿度と融雪水のお陰だ。
この草原はプナと呼ばれていて、アンデス山脈を中心にチリ北部とペルー南部、ボリビアにまたがっている。一見、不毛の地のように見えるが、鳥類は多く、比較的豊かな生態系を保っている。しかし、近年人間の入植による過放牧によって、荒廃化が進んでいるという。
この地域の中心、プトレを基点に花探索を行った。 |
 |
|
 |
ムチシア・ハマータ
Mutisia hamata キク科
キク科の草本。自生地はアンデス山脈中部の乾燥帯。
葉を落とした灌木に絡まって伸び、陽を求めるように頭をもたげていた。
(ベレンロード、標高3550m) |

上は同属の
ムチシア・アクミナータ
Mutisia acuminata キク科 |
| キク科の植物は3万種以上あり、世界各地に広がっている。このため、乾燥地でも多く見ることができる。上記のムチシア属のほかにも |
|
 |
セネキオ・アルゲンス
Senecio algens
高層湿原から流れ出る渓流に沿ってグリーンベルトができる。こうした場所には植物の小さなコロニーが生まれ、ビクーニャなどの野生動物を集める。
(ラス・クエバス 標高4350m) |
(花の拡大)
 |
| |
 |
 |
|
バッカリス・アルニフローラ
Baccharis alnifolia
(プトレ標高3530m) |
ロックカウセニア・ピグマエア
Rockhausenia pygmaea
(ラス・クエバス4350m) |
バルビシア・ミクロフィラ
Balbisia microphylla フランコア科
|
紙細工のような花びらを持つこの花は、蒸散を抑える細い葉を持ち、8ヶ月間雨の降らない環境でも生きられる。
チリ北部の固有種。 |
|
|
| (ベレンロード、標高3380m) |
|
 |
|
砂漠の植物と言えばサボテン。とても普通の植物とは思えない姿かたちだが、れっきとした被子植物で花も咲き、種もできる。 |
 |
クムロポンティア・ボリビアナ
Cumulopuntia boliviana
 黄花の亜種エキナケア echinacea 黄花の亜種エキナケア echinacea
(ベレンロード、標高3530m)
赤花の亜種イグネセンスignescens
(チュンガラ湖、標高4570m) |
 |
オリオセレウス・バリカラー
Oreocereus varicolor
|
茎全体が羽毛のような毛におおわれている。夜間、砂漠の気温は零下までに下り、凍結することもあるため、この羽毛の布団で保温している。
(ベレンロード、標高3370m) |
|
 |
 |
 |
ツニラ・チレンシス または
アイランポア・ソエレンシー
Tunilla chilensis or
Airampoa soehrensii
柱頭が緑色なのは葉緑体があるのだろうか、それともポリネーター(花粉媒介者)を誘引するためだろうか。
(ベレンロード、標高3540m) |
|
|
サボテンの棘は、葉から水分の蒸散を防ぐため葉が変形したもので、乾燥地でサバイバルするための進化であった(光合成は葉に代わって茎で行っている)。また、動物の食害から身を守る手段ともなっている。 サボテンの棘は革靴を貫くほど鋭いが、更に鋭い棘を持った植物があった。
(靴に刺さるクムロポンティア・ボリビアーナ)
|
 |
|
 |
花弁や葉について細い毛は、一見柔らかそうに見えるが、サボテンの棘より細く鋭いので簡単に皮膚を貫く。これを口にしたビクーニャはギャと叫んで、2度と食べなくなるはずだ。本当に痛かった!
これらはシレンゲ(刺蓮華)科。名前からして痛そうだ。 |
 |
カイオフォラ・クルシフローラ
Caiophora cirsiifolia
(ベレンロード 標高3400m) |
カイオフォラ・ロスラータ
Caiophora rosulata
(パリナコタ 標高4420m) |
|
こんな棘だらけの植物ばかりだと野生動物が生きてゆけないのではと心配になるが、そこは自然の偉大さで、動物に食べられることで子孫を広範囲に散布するしたたかな植物達もいる。その代表選手が・・・マメ科。
センナ・ビロストリス
Senna birostris
日本でも庭木として見かけることが多くなったが、原産地はエクアドルからチリにかけてのアンデス山脈西側。
(プトレ 標高3640m) |
 |
|
人類の移動を可能にした豆
人類の祖先は、ゴリラやチンパンジーと同様、熱帯の森に棲んでいたが、多分、彼らとの競争に負けて林縁に追いやられた。そこは乾燥草原(サバンナ)に続く場所で、ライオンやヒョウなど肉食動物が多くいる場所である。食料は乏しく、植物の根や消化の悪い堅果や豆などであった。こうした厳しい環境で人類が生き延びることができたのは、
- 肉食動物を見つけるために立ち上がることで、2足歩行能力が増加した。
- 豆は野火で焼かれることで消化しやすくなり、食料にできた。また、火を使うことを覚えた。
- 植物の根を掘るのに、枝や石を使うことでを道具を使い始めた。
豆や堅果は高カロリーで保存が可能。また、持ち運びが容易。この3点セット(歩行能力、食料、道具・火)のお陰でグレートジャーニーが可能となった。その経路も、ベーリング海峡(当時は陸地)を除けば、中央アジアや北米プレーリーなど草原地帯で、マメ科の植物が豊富で、食料が容易に手に入った。(草原には狩猟の対象となる草食動物も多い)
―以上は個人的推論です。 |
|
 |
ルピナス・オレオフィラ
Lupinus oreophilus
ルピナスは世界中で見られる植物だが、本種は北部チリの固有種である。
(ベレンロード 標高3720m) |
|
アストラガルス・ミニムス
Astragalus minimus
レンゲソウの仲間で、この属はヒマラヤの高山でもよく見かける。花は1㎝ほどの大きさ。
(パリナコタ 標高4420m) |
 |
|
|
私たちがよく食べる野菜のジャガイモやトマトはナス科の植物だが、アンデス山脈が原産地。
 |
 ダナリア・スピノサ ダナリア・スピノサ
Dunallia spinosa
(プトレ 標高3290m) |
 |
ソラヌム・ニチヅム
Solanum nitidum 
花や実の形はミニトマトに似ている。
(ベレンロード 標高3530m) |
ジャブロサ・スクアロサJaborosa squarrosa
アルティプラーノには集落がいくつか点在する。現在は無人のパリナコタ集落の中を歩いていると、路地に青い花をつけた植物があった。ガイドは初めて見たと言っていたが、ペルーが分布の中心で、チリ北部ではパリナコタ火山の周辺でしか見られない。
(パリナコタ 標高4410m) |
 |
|
砂漠や乾燥地帯には、アフリカ・ナミブ砂漠のWelwitschia(奇想天外)のように不思議な形をした植物が生じる。アルティプラーノでも・・・
 |
アゾレラ・コンパクタ
Azorella compacta セリ科
岩にびっしりと付いた苔のように見えるが、ちゃんとした被子植物。1cmほどの黄色い花が咲く。このサイズになるには数百年かかるという。
(グアジャチレ標高4290m)
|
花(クリックで拡大)
|
|
こちらはミステリーサークル
アルティプラーノ・グラスというイネ科の植物が、洪水時に泥を抱え込み、その水分を頼りに乾燥を乗り切る。
(グアジャチレ 標高4100m)
|
1.jpg) |
|
こんな乾いた大地にも咲く花はある。
砂地の上に直径50cmほどのマット状に盛りあがったコロニーを作る。
花は5弁で、大きさは2~3mm。
種名不詳(プリムラの仲間か?)
(グアジャチレ 標高4100m)
|
 |
|
|
 |
どちらもアオイ科の花。
自生地の風景。
(ラス・クエバス 標高4480m)
|
 |
| ノトトリケ・オブクネアタ Nototriche obcuneata |
ノトトリケ・ルゴサNototriche rugosa |
| |
|
|
|
クインカマリウム・チレンシス
Quinchamalium chilense
水も栄養もない崖地に咲いていたが、そんな環境で生きられるのには理由がある。他の植物から栄養をもらう寄生植物だからである。この種はボロボロノキ科という残念な名前がついているが、それは落葉するとき枝も一緒にボロボロと落ちるからという。この科の植物は南米に多いが、日本にも1種(Schoepfia
jasminodora)ある。
(ベレンロード 標高3610m) |
 |
 |
|
|
 |
バーベナ・ギノバシス
Verbena gynobasis
バーベナはクマツヅラ科の植物で、世界に広く分布するが、本種はチリ北部とペルー南部のアルティプラーノ固有種。日本で見られる園芸種のデュランタやランタナ(七変化)もこの仲間。小さい花が集合する。
本種は水の枯れた川の土手に咲いていた。
(ベレンロード 標高3300m) |
 |
|
最後に、アルティプラーノの宝石 をどうぞ。
ボマレア・ダルキス
Bomarea dulcis
近年、日本の花屋でも見かけることが多くなったアリストロメリア科(ユリズイセン)の花。本種はペルーの海岸地帯が主たる自生地で、アルティプラーノは南限になる。
直射日光を嫌うため、大きく枝を張る木の下陰で、枝に巻き付いて1.5~1.8m程に伸びる。茎の先端に長さ3~4cmのピンク色の筒状の花をランタンのように4,5個つける。
この花の花粉媒介者(ポリネーター)はハチドリで、ホバリングして花の奥の蜜を吸う際、頭に付いた花粉が花弁より突き出た雌しべにつき、受粉する。
(標高3740m 希少種につき場所は秘密) |
 |
|
上記で掲載した以外の花についてはここをクリックしてください。
|
一見、不毛の地に見えるアルティプラーノでも植生はそれなりに豊かであった。これらの植物を糧に野生動物たちもいる。
哺乳類では・・・ |
 |
ビクーニャ Vicugna vicugna
ラクダの仲間で、乾燥や粗食に強い。群れで行動する。
ペルー、ボリビア、チリ北部の高原に生息する。チリ南部やパタゴニアにはビクーニャの倍の大きさのグアナコが野生生息する。 |
 |
| (パリナコタ) |
|
(チュンガラ湖) |
|
アルパカ Vicugna pacos
ビクーニャを家畜化したのがアルパカ。毛を取るために品種改良され、ビクーニャに比べるとずんぐりむっくりして、羊のように見える。漢字で羊駱駝と記される。
子は1頭しか生まず、四季を通じていつでも出産する。近年、過放牧により、アルティプラーノの植生が脅かされている。
肉もステーキとして供され、柔らかく美味しかった。
(パリナコタ) |
 |
ラクダの大移動
ラクダの祖先はおよそ4500万年前に北アメリカ大陸で出現したとされる。いつ、どうやってアジア大陸へ渡ったのかははっきりしないが、スペインで700~600万年前の化石が見つかっているので、ベーリング海峡が陸地化したときアジアへ渡ってきたものだろう。その後、乾燥化・砂漠化にともなって中東やアフリカへ分布を広げていった。一方、南アメリカへの進出はパナマ地峡でつながった300万年前以降となり、比較的新しい。人類は約2万年から18,000年前の最終氷期に陸地化したベーリング海峡を渡り、北米に達したが、北米大陸に残っていたラクダの祖先を食料にし、絶滅させたようだ。そして、ラクダを追って南アメリカ最南端まで到達することになる。
(典拠:Wikipedia、AIによる) |
|
|
 |
チンチラ Chinchilla lanigera
岩場に集団で暮らす。縄張り意識は強く、激しく争うときがある。体長30cmほど。ウサギに似ているが、げっ歯類でネズミに近い。
毛が滑らかで毛皮として珍重されるほか、肉としても利用されている
(ラス・クエバス) |
 |
|
| 湖や小川があるため鳥類は豊富だ。 |
 |
 アンデスフラミンゴ アンデスフラミンゴ
Phoenicoparrus andinus
交互に花を羽ばたかせ、シンクロしてカップルの絆を確認し合う。 |
 |
チリフラミンゴ 
Phoenicopterus chilensis
アンデスフラミンゴより羽色は薄い。 |
| (チュンガラ湖) |
|
(グアジャチレ) |
アンデスガン
Chloephaga melanoptera |
体長70~80cm。尾羽と主翼先端は黒い。
(チュンガラ湖) |
|
chungara1.jpg) |
|
 |
 ナンベイオオバン ナンベイオオバン
Fulica armillata
嘴と背が白い。
泳いているのは
アンデスコガモ
Anas andium andium
|
 |
アナホリキツツキ (学名不詳) 
(どちらもパリナコタ) |
|
コンドル Vultur gryphus
翼を広げると3m以上になる空の王者。鳥類の中で翼幅は最も大きく、上昇気流を捕まえて、省エネで長時間滞空できる。
学名Vulturから分かるように、ハゲタカの仲間で死肉のみを食べる高原の掃除人である。仔羊を襲うと誤解され、毒入り肉で大量に駆除されたため生息数は激減した。
このあと、パタゴニアで死んだ仔羊を食べている現場を見ることができた。
(グアジャチレ) |
|
|
ボリビアとの国境地帯には火山が連なる。温泉や間歇泉があり、温浴施設もある。 |
 |  |
左 ポメラペ火山(標高6,282m)
右 パリナコタ火山(標高6,348m) |
グアジャチリ火山(標高6,071m)
現在も水蒸気を上げている。 |
|
この地下には長さ300km幅200kmに渡る巨大なマグマだまりがあり、火山爆発が連動すると巨大災害を引き起こしかねない。
では、乾燥地帯から南へ移動しよう。 |
 |
チリの首都サンチャゴは、南北に細長いチリのちょうど中間に位置し、抜けるような青空の典型的な地中海気候。また、標高が500mの盆地にある。初夏でも朝夕は涼しく、ジャケットがいるほどであった。隣国アルゼンチンとの国境までわずか60kmで、国境に沿って標高5000mクラスのアンデス山脈が連なる。南米で最も高いアコンカグアはサンチャゴの北北東約100㎞に位置している。
東京から飛行機を乗り継ぎ、24時間かけて到着した翌日、時差ボケ解消のため、市内を歩いた。植民地時代から続くスペイン風建物が多く残っている一方、南米で一番高いビル(300m)やガラス張りのモダンなビルも多く建っている。公園や街路樹も多く、緑の多い街であった。日中は日差しが強いので建物の南側にできた日陰を伝って歩いた。 |
(以下に紹介する花はすべて人の手で植えられた栽培品種)
 |
ジャカランダ
Jacaranda mimosifolia
ノウゼンカズラ科 |
種
 |
ホウオウボク(鳳凰木)、カエンボク(火炎木)と合わせて世界三大花木と いわれている。ホウオウボクは海南島とインドで、カエンボクはグァム島で見たことがある。
ジャカランダの原産地は中南米で、ホウオウボクやカエンボク同様、亜熱帯地域に生育する。サンチャゴでは街路樹としていたるところで植えられていて、木陰には涼しい風が吹いていた。
日本ではシウンボク(紫雲木)またはキリモドキの名が付けられている。熱海市や宮崎県日南市で大規模な栽培がなされていて、観光名所となっている。
かつて主治医をしていただいたA医師は、小泉元首相の中南米訪問に付添医師として同行し、土産にこのジャカランダの種をもらい、自宅に撒いたところ発芽し、順調に育ち、花を付けたとうれしそうに話されていた。写真も見せてもらったが、10年ほど前、がんのため亡くなられた。今回、持ち帰った種をまいてみようと思う。
|
|
|
 |
 アリストロメリアAlstroemeria アリストロメリアAlstroemeria
Peruvian lilyの英語名が示すとおり、南米を中心に南半球に多く自生する。園芸種として世界中に広がっており、日本でも一部は野生種となっている。
|
 |
ディエテス・グランディフローラ
Dietes grandiflora アヤメ科
南アフリカが原産の園芸種。 |
|
グラビエア・ロブスタ
Grevillea robusta
ヤマモガシ科
オーストラリアが原産。バンクシアやブラシの木の仲間。 |
 |
|
 |
アカシア・カロ―
Acacia karroo マメ科
南アフリカが原産。
オーストラリアのミモザも
この仲間である。 |
|
 |
 アリウム・ミレニアムAllium 'Millenium' アリウム・ミレニアムAllium 'Millenium'
ヒガンバナ科の園芸種。英国の種苗家が交配して作った。日本のタマムラサキに近い。
|
 |
ツルバギア・ビオラケア
Tulbaghia violacea
南アフリカが原産。メキシコに帰化し、園芸品種として広まった。これもヒガンバナ科。 |
|
チタルパ
× Chitalpa tashkentensis
ノウゼンカズラ科
タシケント植物園が属間交雑種(Catalpa x Chilopsis)で作ったハイブリッド園芸種。 |
 |
キダチタバコ
(木立煙草)
Nicotiana glauca
ナス科
南米原産でインディオがタバコや薬草として用いた。 |
 |
|
 |

トックリノキ(徳利木)
Brachychiton populneus
アオイ科
幹の下部が徳利のように太くなることから名付けられた。オーストラリア原産。 |
1.jpg) |
レースバークツリー
Brachychiton discolor
左のトックリノキと同種であるが、幹は太くならず、ストレート。幹にレース模様が入ることから名が付いた。 |
|
| ほとんどが南米やアフリカ、オーストラリアなど南半球が原産の植物であるが、こんな花もあった。 |
| 日本や台湾が原産地 |
中国が原産 |
1.jpg) |
 |
| ネズミモチ Ligustrum japonicum モクセイ科 |
ナンテン Nandina domestica メギ科 |
|
これでチリの北半分の花々。次回は緑滴る森林や氷雪をいただいた山岳に咲く色とりどりの花を紹介します。 |





































1.jpg)

















chungara1.jpg)

















1.jpg)
1.jpg)